![]()
![]() 長崎和則のプロフィール
長崎和則のプロフィール
![]()
| 自 己 紹 介 | |
| このサイトを開いているのは、長崎和則です。 ここで、簡単ですが自己紹介をします。 1959年生まれ。龍谷大学大学院文学研究科修士課程社会福祉学専攻(現在は,社会学部社会学研究科社会福祉学専攻)卒業。大学院在学中に、特別養護老人ホームで住み込みのアルバイトをしながら、実習も経験する。2か所の児童養護施設で、児童指導員を経験。その後、精神科病院でPSWとして勤める。 福山平成大学勤務を経て,2005年~川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科勤務 2005年~ 助教授/2007年4月~准教授 2009年3月 高知女子大学大学院(現在の高知県立大学大学院)で博士課程修了 (博士:社会福祉学) 2009年4月~ 教授(現在に至る) 現在は,下記に紹介しているように,地域での活動に参加しながら,ソーシャルワークのあり方についても研究を行っている。 |
|
 襟裳岬でジャンプ |
精神科病院でPSWとして 働いていた時の似顔絵 |
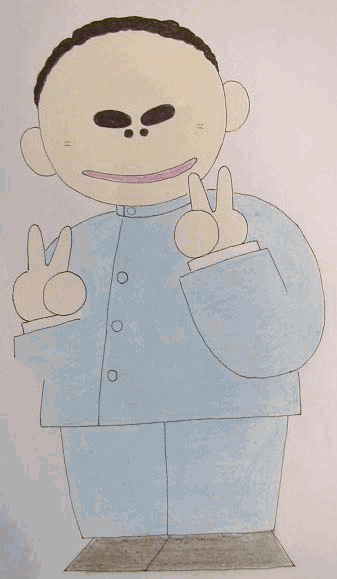 |
|
| 担 当 科 目 | |
| 2023年度の担当科目は,次の通りです。 【学部】 精神障害者の生活支援システム(旧カリキュラム) 精神保健福祉相談援助の基盤 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ・Ⅲ 精神保健ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 精神保健ソーシャルワーク実習 【大学院】 質的研究方法論Ⅰ・Ⅱ(修士課程) 精神保健福祉学特論Ⅰ・Ⅱ(修士課程) 医療福祉学特殊研究(博士課程) 社会福祉学特殊講義(博士課程) |
|
| 加 入 し て い る 学 会 等 | |
| 現在,日本社会福祉学会,日本ソーシャルワーク学会,日本社会福祉教育学会,日本精神保健福祉士協会,日本精神障害者リハビリテーション学会,日本ソーシャルワーカー協会,多文化間精神医学会,等に加入しています。 |
|
| 社 会 的 な 活 動 等 | |
| 「日本ソーシャルワーク学会」 「日本社会福祉学会 中国四国部会」 「西日本M-GTA研究会」HP担当 「中四国M-GTA研究会」副代表 「ソーシャルワークを学ぶ会(長崎塾)」主宰(毎週火曜日開催) 「広島当事者研究会」世話人 「岡山当事者研究」(林友の会)講師 |
|
| 主 な 著 書 等 | |
| 代表的なものを,新しい順に紹介しています。 『スクールソーシャルワーク論-歴史・理論・実践-』 「第8章 メンタルヘルスに関わる問題とスクールソーシャルワーク」 学苑社 2008年. 『精神保健福祉士養成講座 ⑤改訂 精神保健福祉援助技術総論』 「第5章 精神保健福祉援助活動の課題と展望 青年期の発達課題と危機の様相」 中央法規出版 2007年発行 『事例でわかる! 精神障害者支援 実践ガイド -ICFに基づいた精神障害者支援のためのアセスメント,プランニングの進め方-』 「第1章 精神障害者支援を取り巻く動向とICF」 「第2章 ICFに基づいた精神障害者支援のアセスメントとプランニングの技術」 「第4章 事例7 グループホームでの共同生活における支援」 日総研 2006年 「第8章 コラボレーション 2 精神障害を抱え地域で生活するMさんの事例」 ミネルヴァ書房 2005年 「第4章3節 援助関係形成の実技(pp.71-78)」 中央法規出版 2004年 「第5章 実習中の学びとスーパービジョン」 「実習記録ワークシート例」 久美株式会社 2003年 「第7章 事例研究の方法」 久美株式会社 2003年 『精神保健福祉実践ハンドブック』 「第1章 2節 精神保健福祉士の専門性と職業倫理」 「第1章 3節 精神保健福祉士の支援の視点とあり方」 日総研 2002年 『精神保健福祉士の仕事』 「第2章3 精神保健法から精神保健福祉法まで」 「第3章1 福祉職との共通点・相違点」 朱鷺書房 2001年 『ソーシャルウエルビーイング事始め』 「第6章 社会福祉の援助の仕方」 有斐閣 2000年 『社会福祉援助技術論』 「第9章 わが国と諸外国の社会福祉援助技術動向」 学文社 1997年 |
|
![]()
![]()